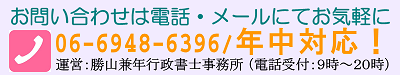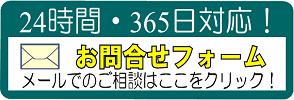お酒には酒税法に決められた品目があります
最終更新日:2025年10月19日 行政書士 勝山 兼年
成分や原料・アルコール度数で品目がきまります
酒類の4つの大別
「酒税法」によると、次の4種類に大別され、17品目に分類されます。
ビールなどの「発泡性酒類」、清酒や果実酒などの「醸造酒類」、ウイスキーや焼酎などの「蒸留酒類」、みりん調味料などの「混成酒類」に別れ、それぞれの酒類の中でも使用原料や製造方法によってより細かく分類されているのです。酒類販売業免許との関係においては、仕入れ先や販売法の他に扱う品目のより必要な酒類販売業免許の酒類が異なってくるのです。特に卸売業免許においては洋酒に比べ清酒やビール焼酎を取扱える免許には取得に高いハードルが設けられています。

(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

主な酒類の名称ごとの品目
- 日本酒
酒税法の品目では清酒といいます。白米を蒸して麹(こうじ)と水を加えて発酵・熟成させて作ります。海外での和食ブームに合わせて、全世界への輸出が増えている品目です。
- 焼酎
製造方法により単式蒸溜しょうちゅうと連続式蒸溜しょうちゅうに判れます。昔ながらの伝統的製法で作られる単式蒸溜しょうちゅうは俗に本格焼酎と呼ばれています。芋や麦の原料の風味を残されています。
連続式蒸溜しょうちゅう高純度に蒸留されているために、原料の臭みをありません。そのため、酎ハイやサワー、カクテルとして飲まています。- ワイン
酒税法の品目では果実酒といいます。ヨーロッパ諸国においてはワインは「ブドウを原料としたもの」の決まりがありますが、日本ではそのような分類はありません。スパークリングワインも果実酒に分類されます。ワインは輸入品も多い酒類で、原料に海外産濃縮果汁を使用されておる物など、それぞれに表示基準があります。
- ビール
商品として流通しているビールといわれるものは、ビール、発泡酒、リキュールです。酒税法の品目でビールと呼べるのは麦芽、ホップ及び水を原料としたものだけです。発泡酒は酒税法でビールと比べ麦芽比率が低いものが税率が低かったことで、流通量が多くなりました。リキュールは焼酎にビール風味を足したもので、さらに税率が低くなるものです。
- ウイスキー
穀物を原料とした蒸留酒のことで、欧州やアメリカではより厳格な定義があります。

酒税法での酒類販売業免許の品目と定義
一般的な名称の他に酒税法で決められた、使用原料や成分、製造方法などにより品目が定められております。品目に応じた厳正な商品表示が義務付けられています。
| 【品目】 | 【定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで)】 |
|---|---|
| 清酒 |
|
| 合成清酒 |
|
| 連続式蒸溜しょうちゅう |
|
| 単式蒸溜しょうちゅう |
|
| みりん |
|
| ビール |
|
| 果実酒 |
|
| 甘味果実酒 |
|
| ウイスキー |
|
| ブランデー |
|
| 原料用アルコール |
|
| 発泡酒 |
|
| その他の醸造酒 |
|
| スピリッツ |
|
| リキュール |
|
| 粉末酒 |
|
| 雑酒 |
|
一般名称は同じでも品目がことなることがある
一般的な名称が同じでも、品目がことなる場合があります。例えば、ビールの品目は「ビール」、「発泡酒」、「リキュール」と3つの品目が並んで販売されています。商品ラベルには品目の記載がありますが、販売する店舗側は棚に品目の表示をする義務はありませんので丹波に他何位一見して区別できません。品目ごとに税率が異なりますので、販売価格帯が違うぐらいです。

卸売免許や通信販売免許を取得する際に、製造メーカーから証明書の発行を受け税務署に提出することになりますが、メーカーが製造している品目により、免許取得後に販売できる品目が変わります。例えば、発泡酒の製造免許のメーカーと取引するのでしたら、ビールは販売できないことになるのです。取引するメーカーがどの品目を製造しているのかを見極めて、免許を取得しなくてはなりません。
- 使用原料や成分、製造方法などにより品目が酒税法で定められている。
- 品目により酒税の税率がことなる。
- 同じ名称の酒類でも品目が異なることがある。